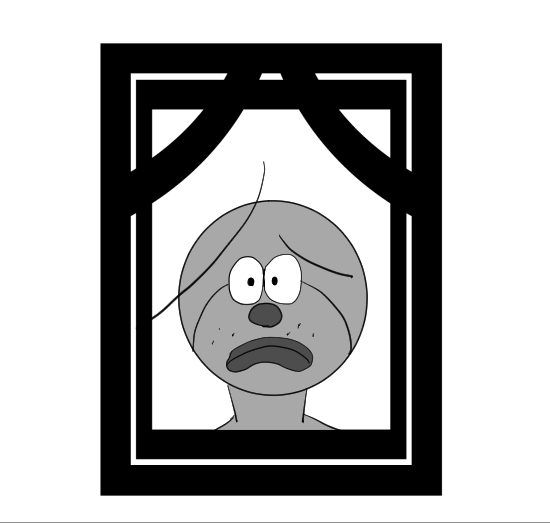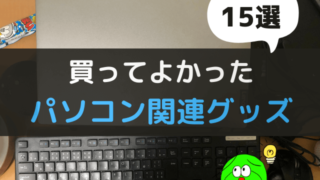ほとんどすべての人が小さな恩義に喜んで恩返しをする。多くの人が中くらいな恩義を恩に着る。しかし大きな恩義に対して恩知らずでない人はほとんど一人もいない。
ラ・ロシュフコー『箴言集』
これは17世紀フランスのモラリスト「ラ・ロシュフコー」の言葉である。
人は大きな恩義に対しては恩知らずであるということだ。
ピンとこない人のために例を挙げてみよう。
恩知らずの心理
落としたペンを近くの人が拾ってくれた。
これには誰しも即座に感謝できる。
失くした財布を交番に届けてくれた。
これも多くの人は素直に感謝できるだろう。
100万円の借金を肩代わりしてくれた。
これも初めは多大な感謝をするに違いない。
だがこの大きな恩義に対する感情は、時の経過とともに複雑になる。
相手の恩を常に忘れてはならないと心がけているうちに、だんだんそれが自発的な感情ではなく強制的な義務に感じてくる。
人には心理的リアクタンスと呼ばれる傾向性があり、自由を制限されるとそれに反発したくなる。
くわえて相手のうちにある「見返りを期待する心」が透けて見えると、なおさら当初抱いていたものとは別の感情が抑えられない。
心の底にある相手を疎ましく思う気持ちと、恩のある人にそんなことを思ってしまう自分への嫌悪感とのあいだで激しい葛藤が繰り広げられる。
そしてこの両者のバトルはたいてい前者が勝利を収める。
つまり最終的には“恩知らず”な態度へと変容するのだ。
罪悪感が強いほど謝れない
これは罪悪感に関しても似たようなことが言える。
肩がぶつかった。
この程度なら大半の人はすぐに謝れるだろう。
仕事でミスをした。
これもよほど重大なミスでなければ抵抗なく謝れる。
ちょっとした口論から相手を傷つける暴言を吐いてしまった。
これはなかなか謝れない。
自分の吐いた言葉が辛辣であればあるほど謝りづらい。
なぜならそれが重大な罪であると自覚しているからだ。
謝ったところで許されない大罪であると誰よりも自分自身が痛感しているのだ。
罪悪感が大きければ大きいほど、人は謝りづらくなる。
その後、罪悪感は二方向に分かれる。
- とにかく自分を責め続け、過去の行いを後悔し続ける
- 自責の念に耐えきれず、後悔が憎しみに変異する
両者の往復を繰り返すケースも少なくない。
以下は【2】の例である。
「なんでこんな酷いことをしてしまったのだろう」 ↓ 「罪を認めたら間違いなく嫌われる」 ↓ 「嫌われるのは辛い」 ↓ 「それならいっそ自分から嫌って楽になろう」
これは精神的ダメージを最小限に抑えるための自己防衛システムであり、たいていは無意識に行われている。
この憎しみは愛情が姿を変えたものなのだが、本人ですらそのことに気づかないことはままある。
もう一つ例を出そう。
仕事で大きなミスをした時、こんな思考が働いたことはないだろうか?
「なんでもっと慎重にやらなかったんだ」 ↓ 「こんな重大なミスは許されるワケがない」 ↓ 「そもそもアイツがあのタイミングで話しかけてこなければ……」
ミスが大きければ大きいほど、自責感はどんどん膨らんでいく。
そして自責感に耐えられなくなり、その責任を誰かに押し付けたくなる。
これは人間の防衛本能からするとごく自然な感情の動きだろう。
スキャンダルを認めない芸能人
スキャンダルを報道された芸能人が、最初のうちは否定していたものの、途中から一転して報道内容を認めるケースは珍しくない。
これに対し、何の利害関係もない第三者が
「嘘をつくなんて反省していない証拠だ」
「どうせ認めるなら最初から認めておけばいいのに」
なんてシタリ顔で言っているのはよく見る光景だ。
このような第三者を見るといつもこう思う。
この人には感情の機微がわからないのかな、と。
罪悪感を抱いているからこそ否定するんだろうに。
とっさに保身のために嘘をついてしまうことなんて人間なら誰しもあるだろうに。
芸能人の「保身」を自分には無縁の悪徳であるかのように批難している人間は非常に多い。
だが保身をしない人間なんてこの世にいるのだろうか?
自分が一番大事なのは誰だってそうだろう。
もし「自分は違う」と思う人間がいるとしたら、それは自省能力のない人間か健忘症を患っているかのどちらかだ。
我々の美徳は、ほとんどの場合、偽装した悪徳にすぎない。
これも冒頭で紹介したラ・ロシュフコーの言葉だが、自らの善良さを疑わない人間には一生分からない感覚だろう。